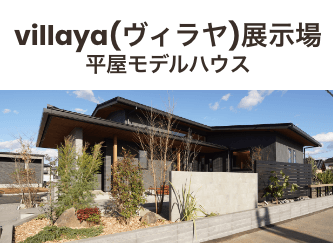こんにちは、彩+houseです。
日本では、将来の発生が懸念される南海トラフ巨大地震など、大規模な地震は日本各地で周期的に発生しています。
茨城県においても、30年以内にM7クラスの地震が発生する確率が約80%とされており、決して他人事ではありません。
日本に住む以上いつどこで起こるかわからないため、「地震に強い家づくり」は、これからの時代に必要不可欠なテーマです。
では、具体的にどのような家が「地震に強い」と言えるのでしょうか?
そのカギの一つが、耐震等級3を取得するための2つの計算方法「壁量計算」と「許容応力度計算」です。今回は、その2つの計算方法の違いについて解説していきます。
◎耐震等級3なら安心は間違い?実は取得方法で性能に違いが出る

耐震等級3は、現行の建築基準法で定められた最高ランクの耐震基準で、消防署や警察署と同レベルの耐震性を誇ります。
しかし、耐震等級3を取得する方法には「壁量計算」「許容応力度計算」の2種類があり、どちらを選ぶかによって、実際の耐震性能に違いが生じることがあります。
①壁量計算(簡易計算)
建築基準法で定められた最低限の基準に基づき、「壁の量」だけを見て耐震性を判断する方法です。
設計の手間が少なく、比較的コストを抑えやすいのがメリットですが、建物全体のバランスや力の流れは考慮しないため、建物ごとに耐震性能にバラつきが出る可能性があります。
②許容応力度計算(詳細計算)
地震や台風などの建物全体にかかる力を細かく計算し、それに耐えうる一つ一つの部材の強度(応力)を詳細に検証する方法です。
計算は複雑で、壁量計算より時間やコストもかかりますが、建物全体の力の流れを把握した耐震設計ができるため、より安全性の高い構造にできます。
このように、許容応力度計算は壁量計算よりも計算の種類や検討項目が多く、さまざまな角度から耐震対策を考えることができます。そのため、耐震等級3の家を建てるなら、許容応力度計算を取り入れることで、より耐震性に優れた家を実現できます。
◎彩+houseは全棟で「許容応力度計算」を実施!

彩+houseでは、すべての住まいで「許容応力度計算」を実施し、標準仕様で「耐震等級3」をご提供しています。
実は、耐震等級3をオプション扱いにしている住宅会社も少なくありません。コストを抑えるメリットはあるかもしれませんが、私たちは「命を守る住まいづくりにおいて、安全は最初から備わるべきもの」だと考えているので、耐震性にも妥協はせず、安心安全な家づくりをお届けしています!
本日は地震の揺れに「耐える」家づくりをお話ししましたが、その揺れ自体を「抑える」ことも、住まいの安全には欠かせません。
そのため次回は、地震に負けない家づくりの2つ目のポイント、制震ダンパーの「MIRAIE(ミライエ)」について解説します。
★彩+houseの家の耐震性について詳しくは、YouTube動画をご覧ください
『【注文住宅】巨大地震の備え!家づくりのプロが耐震で大事な2つの事を教えます!』
============================

*この記事を書いた人
プランナー 石川 直弥 / スタッフインタビュー